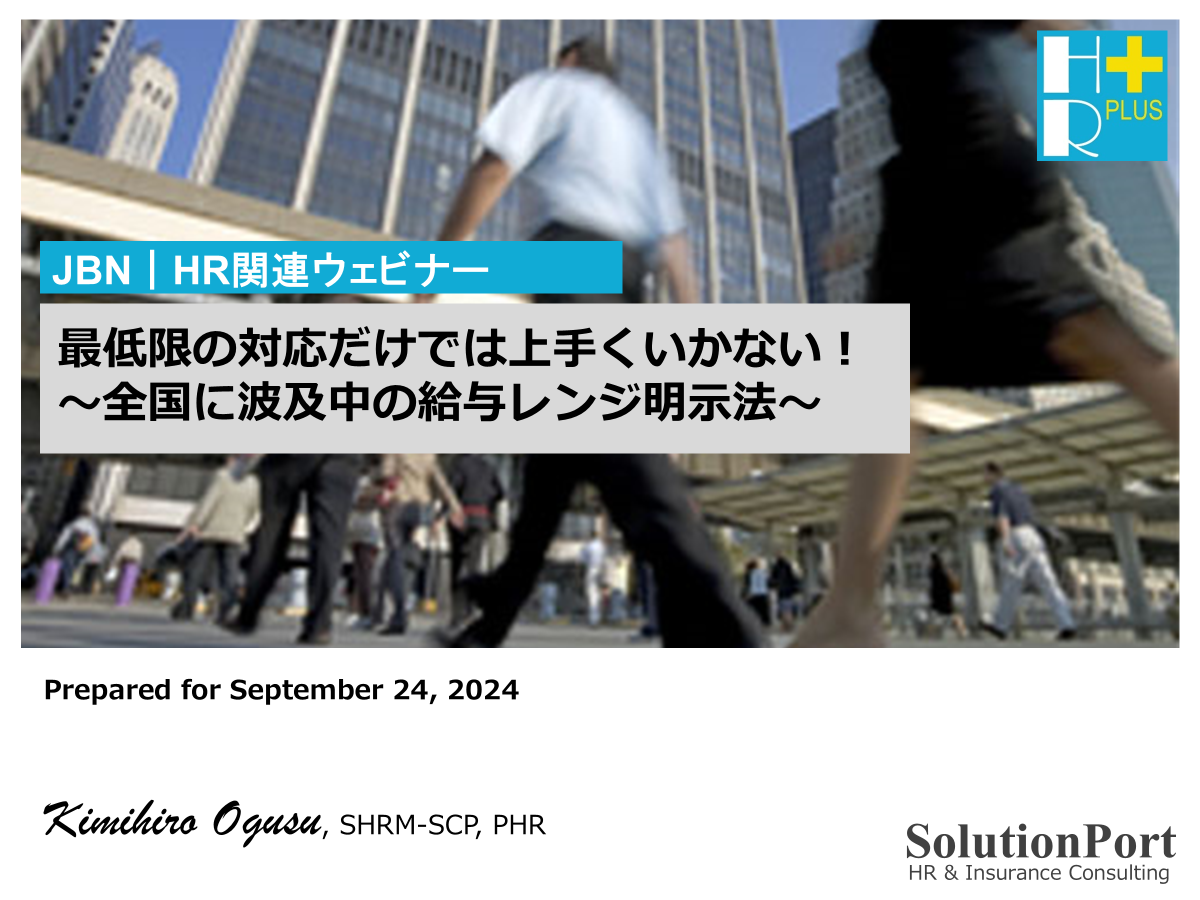(2017年3号)
前回のNews Letterでは、H1-Bビザの今後の見通しに伴う人材確保に関して触れさせていただきましたが、ビザの有無にかかわらず、良い人材を確保する事は企業にとっての大命題とも言える点かと思います。アメリカでは、人が組織に継続して所属し続ける事をリテンションと表現しますが、今回はそれを実現させるためにはどの様なポイントがあり、どういった部分に見落としがあり得るのかを考察してみました。
期待する待遇のトップは給与ではない
アメリカにおいて、「働く」事は生活を回して行くための金銭を得る行為であり、日本の様な「社会人」という概念はありません。そのため、社会のために尽くす事や自身の成長というよりも、シンプルに待遇が優先される考え方が主流です。一般的な流れでは、より高い給与を貰うためには職務経験が必要で、特に経験年数が見られるため、自身の目指すキャリアに沿った業界/職種で働き始めた3-4年後に「転職=給与アップ」という考えのもと次のステップを見据えます。
しかし、20-30代の60%が転職を検討しているとされている一方で、一定の給与やキャリアに届くと少し異なる傾向もある様です。会社に求める金銭的待遇の調査では、給与がトップ、次に健康保険やリタイアメントプランが来るというデータもありますが、非金銭的な待遇も含めた調査では給与や福利厚生よりも高く評価されているものがあり、それはRespect (being appreciated and valued in the workplace)やAchievement (sense of purpose and meaning from your work)、Balance (opportunity to balance work time with family needs)になります。
ちなみに、対象をMillennial (ミレニアル世代 =1980年前後から2005年ごろにかけて生まれた世代) に絞った調査では、Cash BonusよりもTraining & DevelopmentやFlexible Working Hoursの方が求められているというデータもあります。蛇足ですが、これは将来高い給与を稼ぐための投資なので、待遇を優先するためという考えに基づいているのかと捉えています。
いずれにせよ、個に対する感謝や認知、意義を感じながら仕事をして達成する、ワークライフバランスが整っているなど、労働「環境」がリテンションの大きなポイントとなっています。
環境を作る上で重要となる期待値の共有
毎日来る職場が良い環境であれば嬉しい事であり、上述されているポイントが揃っていればそこを離れる理由は多くはないはずですが、そう簡単に実現されるものでもありません。例えば、個に対する感謝や認知に関しては仕事が評価されるという点も含まれますが、社内に成果を測る基準や制度がない、あるいは曖昧だったとすると、感謝や認知をする事は難しいかもしれません。
また、自身の仕事に意義を感じながら仕事をして達成するためには、明確な目標設定や職務に対する深い理解や愛着が欠かせませんし、成長のための研修や能力開発には、必要な経験ができるプログラムが欲しい所です。
そのため、正しい制度は環境を作るための大きなポイントとなり、更にはそれによってもたらされる従業員と会社側の正しい期待値の共有がある状態が、良い環境と呼べるものなのかもしれません。
ただし、一度に全ての制度を整える事は難しいため、現状を踏まえた上で優先順位を付けて行くのが良いのかと思います。例えば、Millennial世代がいないのに研修にばかり力を入れても期待する様な効果は出ないでしょうし、職務内容や日々の業務が整理されていない状態で評価指標を作る事も同様の事が言えると考えられます。
また、特に規模の小さい組織では、既存メンバーで長期的に運営して行くのか、ある程度のサイクルで入れ替わりが生じる事を前提とした形を取るのかなど、自社のスタンスを明確にする必要があります。つまり、組織運営の方向性、現在の従業員構成、職務内容や日々の業務が整理されるとようやく制度を考える基盤ができ、制度が充実する事によって期待値が正しく共有されやすくなります。
モチベーションを落とす作業ストレス
ここまでに挙げたものは組織運営や制度に関する部分ですが、従業員が行う業務や作業にも大きなポイントが隠されています。そもそも、職場でのストレスはExcess Workload (仕事量の過多)から生じるものが多いとされていて、その積み重ねが自身の職務に意義を感じ愛着を持つ事と反対のものへと導いて行く様です。
もし本当に仕事量がアンバランスであれば、職務内容などの見直しをすれば解決する事かもしれませんが、制度や仕組み上で目に映りにくい細かい作業の積み重ねも、仕事量を知らぬ間に増やしているという事も考えられるため注意が必要です。
例えば、社内システムを導入しているのに最後はアナログで入力や計算をしなくてはならない、イントラがあるのにアクセスがスムーズではないために結局本人に頼んでデータを送って貰う、更には、椅子と机の高さが合っていないのに変えて貰えない、などの状況も挙げられます。
この様な目に映りにくい細かいストレスの積み重ねによって、従業員のモチベーション低下が引き起こされる場合もあり、「何でこうなのだろう・・・」「本来こうではないのか?!」と感じる事や、「こんな当たり前の事が・・・」「他社ではこうではないかもしれない」という思いに繋り、結果として新しい環境へと動き出してしまう事もあるのかもしれません。
つまり、職務内容が整理されている事や明確な目標設定などの制度が整っているだけでは、リテンションが実現する環境としては不十分な可能性もあり、作業ストレスは見落とされがちなポイントになり得ます。
今回の内容を総括すると、リテンションが実現する環境には「期待値の共有」と「作業ストレス」の度合いが大きく関わって来ると考えられます。通常、リテンションの話題になると待遇や制度などに対して言及される事も多いかと思いますが、その点を大事にしつつも、目に映りにくい部分に見落としがないかというポイントにも着目して、社内環境に関して考えられてみてはいかがでしょうか。
本内容は人事的側面から実用的な情報を提供するものであり、法的なアドバイスではありません。また、コンテンツ(文章・動画・内容・テキスト・画像など)の無断転載・無断使用を固く禁じます。