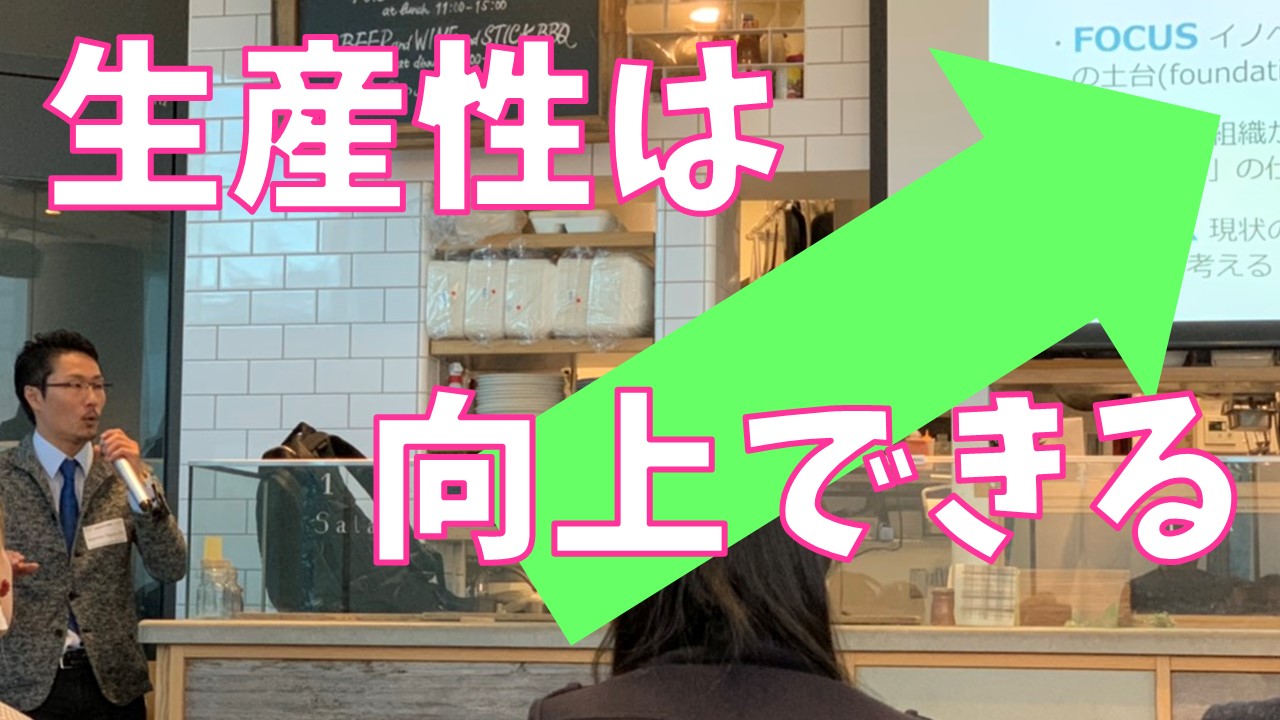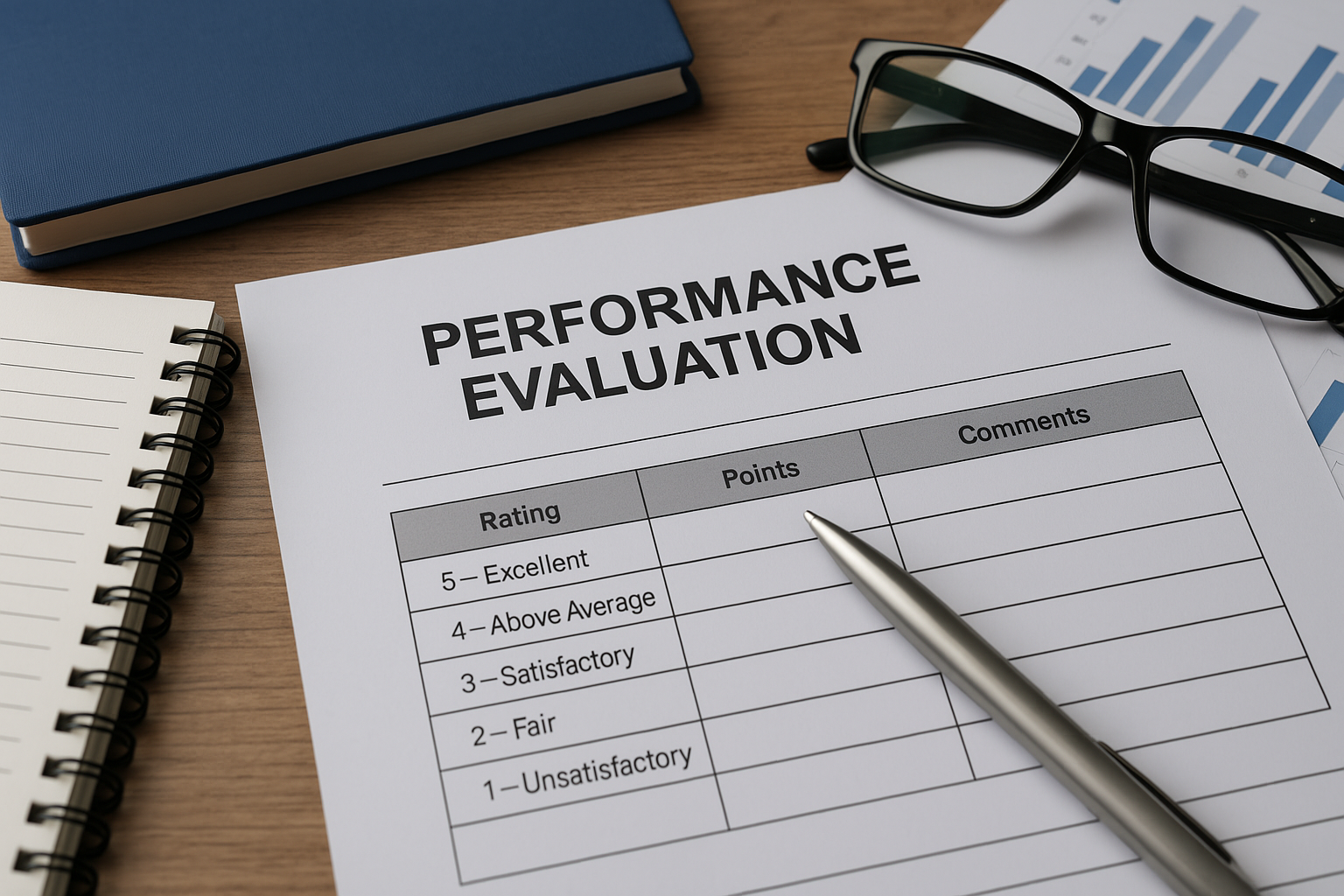Kimihiro Ogusu|2015年
アメリカにある企業は、1月にFiscal Year (年度)が始まる形を取っている所がほとんどです。(一部の在米日系企業は4月) そのため、年度末になると決算や人事編成など、考えなくてはならない事が多く発生する時期を迎えます。
人事まわりに着目すると、この時期といえば評価/昇給に関して頭を悩ませるマネジメントの方も多いかと存じます。
昇給に関しては、以前の記事(昇給はCPIには比例していない?!)で書かせていただいた様に、毎年必ず上げなくてはならないものではなく、評価に関しては、やはり「うまくいっていない・・・」という事をよく耳にします。
では、どういった部分が「うまくいっていない」のでしょうか。またどの様にすれば「うまくいく」のでしょうか。
私がお聞きする「うまくいっていない」ケースは、従業員が「自分はよくやった」と言い張り昇給を求めて来る、あるいはマネジメントサイドが求めている成果ではないが分かって貰えない、といった様な内容が大半を占めています。要するに、双方の理解に何かしらのズレがあるという事です。「ちゃんと言っている」のにも関わらず。
そこで状況を一歩引いた形で考えてみましょう。皆さんも最初に思いつくであろう要素は、言語の壁の部分かと思います。確かに、英語もそこまで流暢ではない方も多いでしょうし、アメリカ流のコミュニケーションの取り方に不慣れな方もいる中で、「ちゃんと言っている」つもりでもしっかり伝わっていない事も考えられます。とりわけ、業務に対する期待値や責任などは、余程整理がされていない限り、言語の壁がなかったとしても簡単には伝わらないかもしれません。
また、従業員が「分かった」と言っているのは、その人自身の解釈である、もしくは愛想を良くするために言ってくれているだけという事もあるため、その時点では理解が同じレベルで共有されていない事もあります。
ポイントとなるのは、「伝えたい事に対して、きっちり伝わるだけの準備ができているのか」という部分になります。もちろん言語の壁やコミュニケーションの取り方の部分も欠かせませんが、今回はツールや指針、データといった方面から「準備」を考えてみます。
給与交渉に関しては、事前にデータなどを準備する事が重要です。従業員が交渉を持ち掛ける際は、自身で調べたリソースのデータを持って来る場合が多く、マネジメントサイドもそれに対して準備が必要となります。そのリソースは、インターネットにて無料で手に入るSalary.com、Glassdoor、IndeedあるいはWord of Mouth (知人から得た情報など)からの情報がほとんどですが、そういったサイトを覗いてみた事はありますでしょうか。
話し合いをするのであれば、相手の考え方を理解しようとするプロセスは重要で、そういった姿勢はコミュニケーションの基本ではないのかと思います。今回は、事前にそういったサイトを少し覗いてみるのも良いかもしれません。
もちろん、そのサイトを見るだけでは何の準備にもなりませんので、そこから得られるデータを見て、それが正しいのか、その給与と合わせたいのか・・・などを考察する必要があります。
何故なら、そのデータが正しいのであれば給与をそれに合わせる必要性が生じ、違うと思うのであればどの様な理由でそれが違うのかを説明できなくては、従業員に納得して貰えないからです。
そのためには理路整然とした説明が必要で、給与に対する会社側の正しい見解を堂々と述べられなくてはなりません。給与の場合は、今回提示している金額が何故適切なのかという部分になります。
例えば、「ウチは基本給は少し安いかもしれないが、保険が良い」のであれば、相場よりも実際にどれ位給与が低くて、保険がどれ位良いのかを理解していなくては話になりませんし、その状況がどれ程従業員を満足させられているのかを考える必要があります。
恐らく、「うまくいっていない」会社の場合は満足していない事が多く、課題がウヤムヤになってしまい会社側と従業員側の双方がモヤモヤを抱えてしまうケースもあるのかと思います。
そういった状況を防ぎ理路整然とするためには、まずは基本給に関して正しい理解する事が不可欠なので、今年は人事考課の前に、基本給をしっかりと把握しておきましょう!
ちなみに、上述したサイトから得られる無料のデータの中には、利用者が自身の給与を入力する事で成り立っているものもあり、実情よりも高い金額が出る場合が多いため、必ずしも正確なデータである訳ではないので注意が必要です。基本給の正確な市場相場のデータを得るには、その会社の地域、業種/業界、職務内容から判断する必要があり、その様な緻密なデータを入手するためには、弊社の様な所に依頼する事が推奨されます。
加えて、キャリアパスや育成方針などが提示できると更に効果的です。どういう事ができる従業員になって欲しくて、そうなった際には給与はいくら貰えるのか、そのために何をすれば良いのかという部分を明らかにする事がポイントで、可能であれば現状の給与だけでなく、次のステップの相場も知っておくとより理路整然であると言えます。(前回のNews Letterに書いた、”人員が回転する組織なのか”の部分にも関連します)
期待値を明確にするには、まずはそのポジションの機能(ファンクション)を整理し、その上でその各個人に対するRequirementを定める形になります。そうなった後に、初めて話し合いができる土台を作り出せます。
また、後になって「本当はこれをやって欲しかった」「これもあなたの仕事だった」と言わざるを得ない状況を防ぐべく、その期が始まる前にRequirementを明らかにし、それに対する理解を共通のレベルに持って行ける様、最大限努めていく必要があります。
さらに、日常の業務がそのRequirementから逸れ過ぎない様、期の途中でも修正できる場を設け、期末にダメ出しをしなくて良いようにすれば、お互いにとって利点があります。
そうする事によって信頼は深まり、より建設的な話ができる様になり、ひいてはモチベーションや生産性も高まって行く事も期待できます。生産性が高まれば、従業員の仕事の量や難易度が上がる事も考えられるので、それによって給与を上げる要素も生まれるため、成長する会社には欠かせない形とも言えます。
師も走る季節を目前にして、なかなか色々と考える余裕が無いというジレンマを抱える所も多いかと思いますが、評価時の問題や人間関係の摩擦を防ぐ事によって、評価時やその後陥ってしまう忙しさは緩和できるかもしれません。
何よりも、モチベーションや生産性の向上も期待できるため、今年はしっかりとした準備にこだわってみるのはいかがでしょうか。
本内容は人事的側面から実用的な情報を提供するものであり、法的なアドバイスではありません。また、コンテンツ(文章・動画・内容・テキスト・画像など)の無断転載・無断使用を固く禁じます。