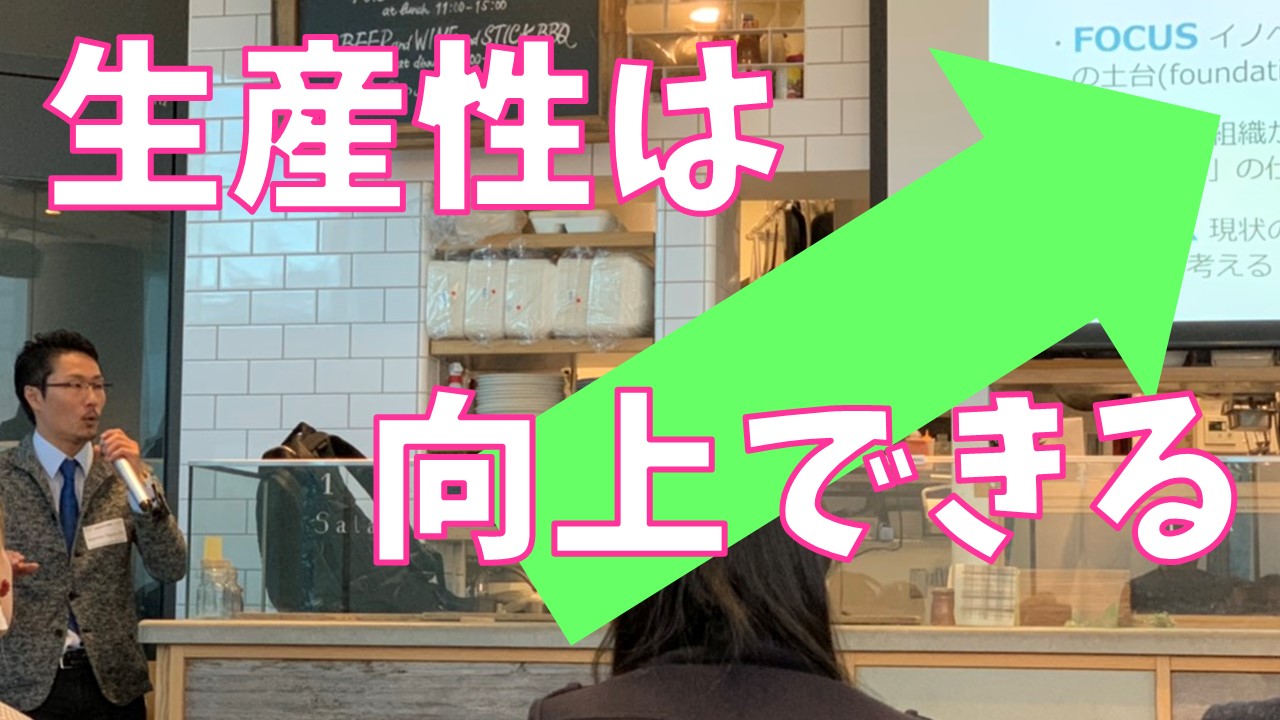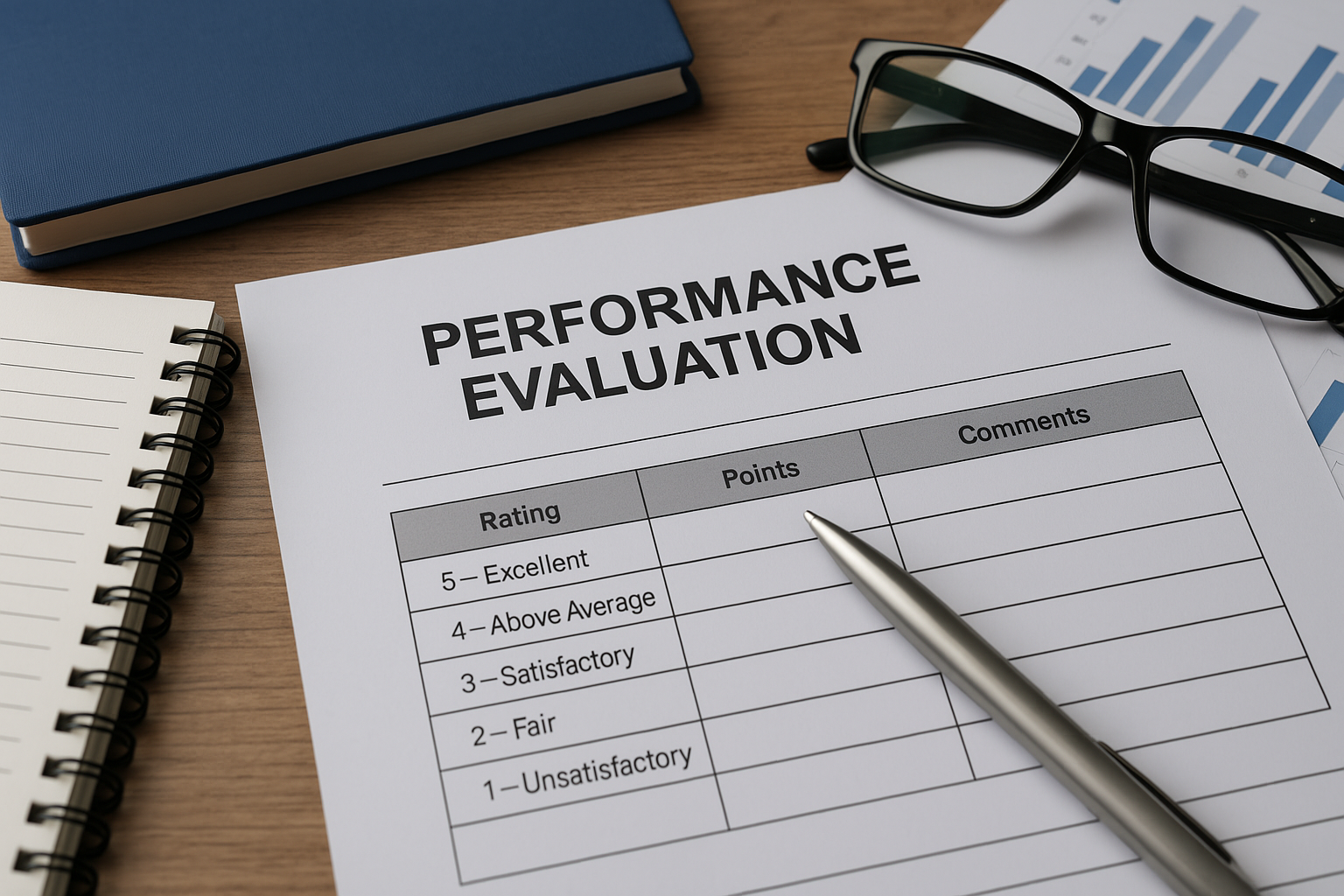Kimihiro Ogusu|2016年
前回、前々回と渡って書かせていただいた「アメリカでの評価」に関して、最後に取り上げたいのがコミュニケーションの部分になります。これは言語という側面もそうですが、どちらかというとビジネス環境の中での文化面やマネジメントの在り方の違いなどを理解する事が重要になるため、今回はそういった切り口で書かせていただきます。
皆さんがアメリカに来られてから散々聞いている部分かとは存じますが、まず初めに挙げられるのが雇用形態や雇用スパンの違いになります。最近は多少変わって来ているという見方もあるものの、日本での基本的な考え方は終身雇用をベースにしたものが主流であり、大雑把に言うと、会社に入ってから定年までという約30-40年というスパンで給与や責任や仕事量などが与えられて来ました。
また、業務も自身の職務範囲というよりは、「上司に言われた事をやらなくてはいけない」という風潮もあったため、時には周りの人よりも多く仕事をこなす人もいたのではないでしょうか。また、仕事を多く頼まれる人の中には、結果として後に周りよりも出世するというケースもあり得ましたが、それは雇用を長いスパンで考えられるから成り立つやり方だと考えられています。
しかしアメリカでは、At-Will(任意雇用)がベースで組織が成り立っているため、従業員の雇用スパンは必ずしも長いとは限りません。(任意雇用=雇用側がいつでも従業員を辞めさせられる、従業員側がいつでも辞められる平等な雇用関係) また、何よりも職務(ポジションとその職責)をある程度定めた形で組織が成り立っているため、前述の様に特定の人が周りよりも多くの仕事を背負う場合は、その人の職務内容から離れていないかという点を気にする必要があります。
例えば、社内の融通が利く人ばかりに作業が集中する事がありますが、職務内容から乖離していると不当な要求になってしまい、他に同じポジションの人がいたとしたら不公平な扱いという様にも捉えられます。また、エキストラな仕事を頼んだ際に評価や感謝が足りず、モチベーションの低下を促してしまう事も見受けられます。そういった場合でよく耳にする話としては、そのキープレイヤーともなりうる優秀な社員は辞めて行ってしまい、人材の流出にも繋がってしまうというものが筆頭に挙げられます。
もう一つ日米で大きく異なるのがマネジメントの在り方で、日本では末端の従業員に対して業務のプランや取り組み方あるいは改善案を求める事もありますが、アメリカではそれはマネジメントが整理して指示を出すものであるという考え方が一般的です。もちろん、更に業務を効果的にするためにアイディアを求める事はありますが、マネジメントにある程度クリアなビジョンがあった上での話になります。
また、「従業員に考えさせる」という場面であれば、それを丸投げにするのではなく一緒に考えるか、権限移譲をして任せきるかどちらかになる事が多いです。そういった形の交通整理ができるか否かで組織のまとまりは大きく左右され、できない場合はアメリカ型のマネジメントに不慣れであると判断されてしまっても仕方ないのかもしれません。
こういった背景を意識しながらコミュニケーションを図って行く中で、実際に指示を出すあるいは会話をする場合は、話す順番や内容の整理の仕方が大事になって来ます。アメリカで試験勉強などをされた人は感じた事があるかもしれませんが、日本とアメリカでは情報の出し方や順番が違うので、話しをする際は「ストーリーテリング」ができるかどうかを意識する事が大切になります。
アメリカにおけるストーリーテリングの形として一般的なのは、一つの事に対して最後まで話したら次の項目に移るパターンが多いですが、相手にとって分かりやすい順番で話す事を意識していれば良い様にも思います。ただし、評価というシーンにおいて疎かにしてはならないのは、評価する側の準備という部分です。
それは、自分は相手にとって評価するべき立ち位置になれているのか(肩書だけではなく)、そこに信用はあるのかという部分であり、具体的にはマネジメントというファンクションを満たしていると思われているのか、また英語はしっかりと話せているのかという要素も含まれます。
例えば、アメリカに赴任するにあたって日本側から言われている職務をしっかりこなしていても、アメリカの組織という観点で見た場合にもし欠けているファンクションがあるとしたならば、アメリカの組織で働いている従業員からすると、物足りない部分が生じる事もあるのかもしれません。また、言語面での不足があって、伝えたい事がお互い伝わらないケースも十分に考えられますが、そういった事を少しでも無くして行く事がより風通しの良い組織を作り上げていく秘訣なのかもしれません。
つまり、マネジメントという立ち位置にある人が「アメリカに来てトップを張っている」事を大切に思い、困難な事に対しても正面から向かい合う覚悟を示す事というリーダーシップの要素は欠かせないものなのです。
今回のトピックスをまとめると、コミュニケーションというのはストーリーテリング、ストーリーテリングというのは情報を整理して伝える、情報を整理するというのは文化背景や自身の立ち位置を理解するという事になります。
新年が明けて今年の目標を決められる人も多いかと存じますが、その中で今年は「コミュニケーション」という部分も選択肢の一つにされてみるのはいかがでしょうか。
本内容は人事的側面から実用的な情報を提供するものであり、法的なアドバイスではありません。また、コンテンツ(文章・動画・内容・テキスト・画像など)の無断転載・無断使用を固く禁じます。