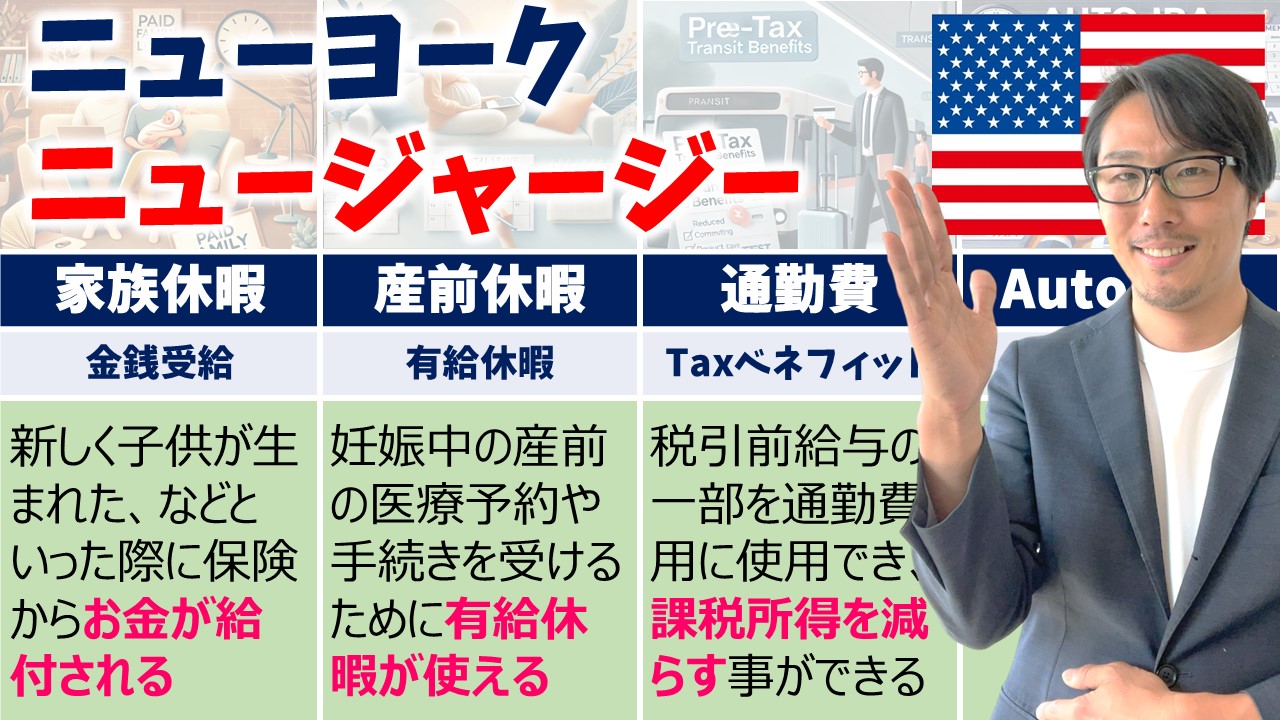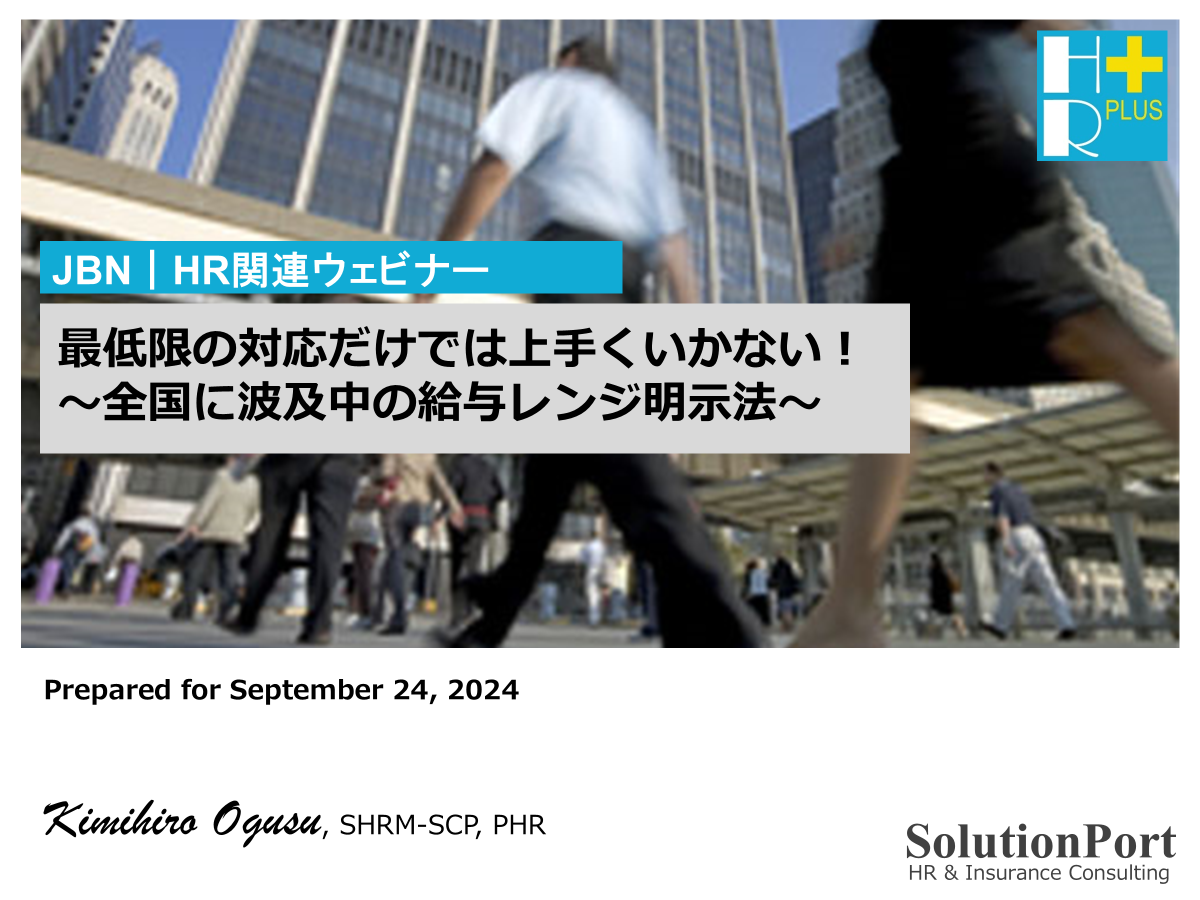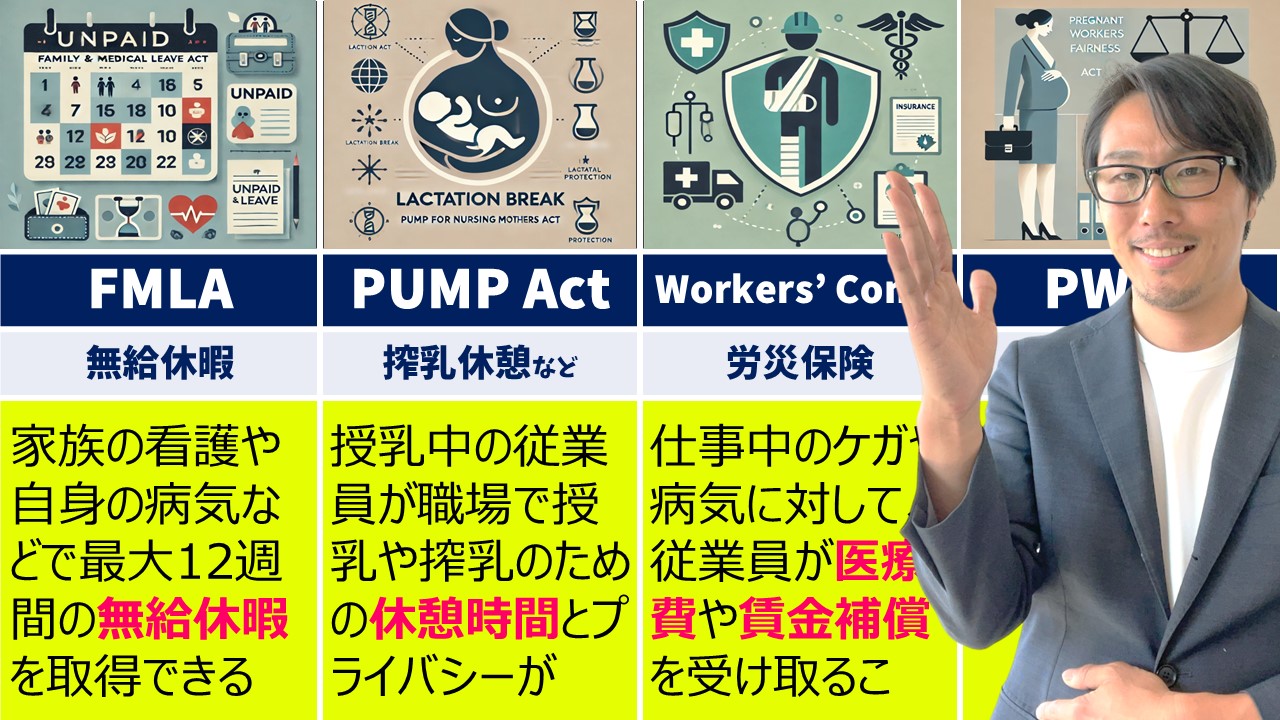Kimihiro Ogusu|2015年
在米日系企業の皆さまに昇給方法に関してお聞きすると、「毎年CPIに応じて上げている」とお話しいただく事があります。また、それに付随して「長年働いている社員の基本給がインフレしてしまっている」という問題点もパターン化された様に耳にします。
その背景には、会社としての昇給方法が確立されていない、あるいは前任者や前々任者のやり方に倣っている事などが考えられますが、ポイントとしては「対象者の基本給レンジを考慮していない」場合が多い様に見受けられます。(ちなみに基本給レンジは、対象者のポジション/職務内容と地域や業界を加味した市場相場から出される事が一般的です。
そもそも、CPI(Consumer Price Index =消費者物価指数)の前年度比の数値を年間平均で見てみると、2013年は1.5%、2014年は1.6%、2015年(1-6月)は-0.05%となっています。前述の様にCPIに応じて給与を上げるとなると、マイナスになっている今年は減給になるのでしょうか。
恐らく、そういった対応を取られる所はほとんど無いのかと思います。
では一体どの様にすれば良いのかという部分ですが、昇給を検討する際のポイントはいくつかあります。その一つとして、アメリカの一般的な企業が参考にしている「昇給予算の上昇率」が挙げられます。各調査会社や機関(Mercer、SHRM、WorldatWorkなど)が出している統計によると、ここ数年の次年度に対する昇給予算は3%程度となっています。(2013-2014年と2014-2015年はともに2.9%-3.0%でした)
2015-2016年に関しては給与は上昇するという市場の期待があり、今の所3.0-3.1%という数字が出されています。ただし、案にその数字を反映させるだけが正解とは言えないのが、昇給の難しい部分です。
会社の昇給予算の上昇率が仮に3%だったとしても、それを従業員個々の昇給率に落とし込む際には、評価を基に差がつけられるケースが一般的です。そのため、「普通(期待通り)」の人を3%の昇給という基準に置き、評価の「良い」人は4%-5%、「期待値以下」の人は1%あるいは昇給なしという事も考えられます。
もう一つ考えなくてはならないポイントが、「現在の給与が市場相場と比べてどうなのか」という部分です。例えば、市場相場としての給与レンジが仮に$34,000-$48,000だったとして、同じ「普通(期待通り)」という評価がなされた場合、基本給が$36,000の人と$45,000の人では、昇給率が異なって来るケースは多いはずです。(給与レンジの上限に遠い方が、昇給の幅が大きくなる可能性が高い)
そもそも、利益が増えていなければ固定給を上げる事は難しいため、会社の状況も加味する必要もあります。(その場合はボーナス等で一時金として報いる形も考えられます)
また、これは余談になりますが、最近全国的に広がるファーストフード店の最低賃金の値上げも少し気になる所ではあります。NYでは、ファーストフード店の最低時給がここ2年で$7.25から$8.75に上がり、今年に入って$9.00台に突入したとされていますが、これを更に上げて$15にするという動きがあります。(全国に30店舗以上構えるファーストフード店に限られ、2018年に向けて段階的に上げていき、2021年6月1日までに全国に普及となる見込み)
これを仮に1日8時間働くNon-Exemptの従業員として換算すると年収$31,200になり、リーダーになると$2.00程度時給が増すと考えると、年収は実に$35,000程度にもなります。もちろん、それは最近の話題のニュースの一つに過ぎないため昇給の検討要素とはならないかもしれませんが、最近は失業率の改善も重なり、給与の上昇傾向が強いといいう印象は拭えません。いずれにしろ、今年は例年にも増して市場の動向から目が離せなくなりそうです。
その様な環境の中、昇給を検討する上で最も重要となるのは、適性の給与レンジを知るという事になるかと思います。まずは現在置かれている状況を把握し、それを基に昇給プランを考えていくと今後の方向性も見えやすくなるのではないでしょうか。
本内容は人事的側面から実用的な情報を提供するものであり、法的なアドバイスではありません。また、コンテンツ(文章・動画・内容・テキスト・画像など)の無断転載・無断使用を固く禁じます。