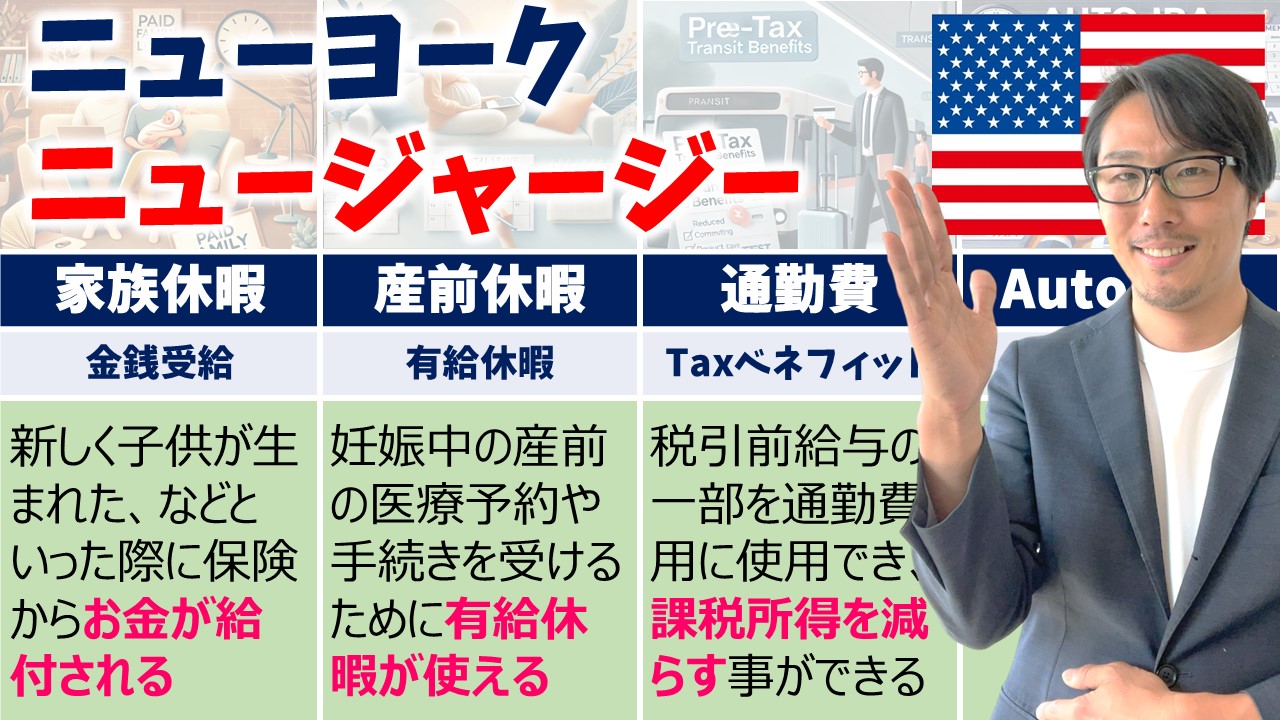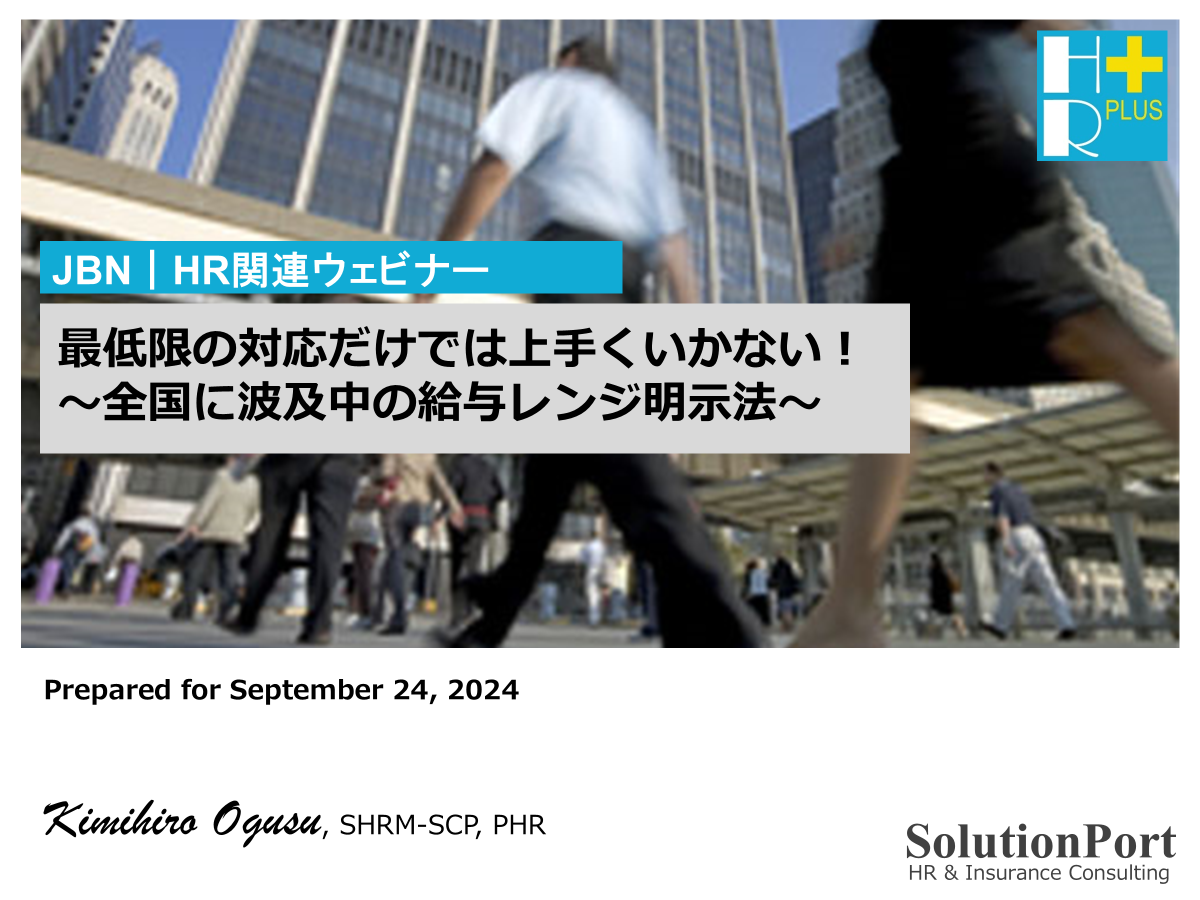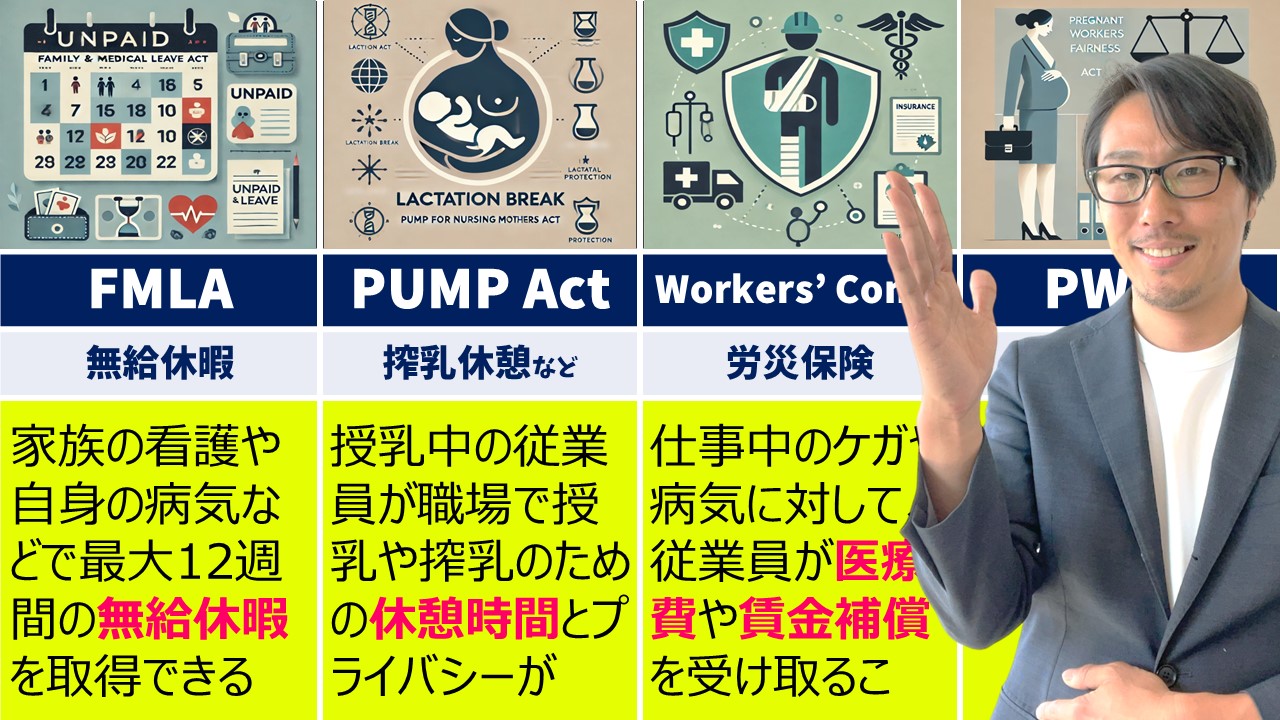Kimihiro Ogusu|2015年
在米日系企業の皆さまは、組織の大小に限らずHealth・Dental・Visionの保険を提供している所がほとんどです。最近はACA(Affordable Care Act: 通称オバマケア)の影響で、カバレッジ内容の変更や自己負担の増加などがあるものの、Health Insuranceに関しては今もなお自己負担率やDeductibleの低さ、および扶養家族のカバー率が高い事など、内容が充実していると言われています。
では一体なぜ保険を手厚くしているのかとお聞きしてみると、「当社はそこが売りで、高い競争力をもたらしている」というような内容のご返答を多く耳にします。そこで今回の考察のポイントになるのですが、果たしてその競争力はどこまで有効なものなのでしょうか、そして充実度が高い保険はどこまで必要なのでしょうか。
Aflac社のリサーチによると、福利厚生が充実する事によって80%の人がそれをポジティブ捉え、74%もの人が仕事への満足感に繋がると答え、67%の人が「仕事の生産性に繋がる」と考えています。そのため、保険関連が福利厚生の大きな割合を占めるとすると、確かに保険を充実させる事は効果的だと言えると思います。
ただし、重要なのは「その競争力はなぜ必要で、誰に対してのものなのか」という部分になります。それは新しく採用する時のためのものなのでしょうか、はたまた、現在いる人員に対するリテンションプランの一環なのでしょうか。
まず考えてみるべき点の一つとしては、「現状の自社組織は新しい人員が頻繁に入って来る会社なのか」という事が挙げられます。もしそのようであれば、応募者が企業の待遇を比較する際に見る福利厚生は重要なので、保険を充実させる事で競争力は高まります。(求職中の59%の人は多少基本給が低くても福利厚生が充実している会社を選ぶ傾向があります)
しかし、そのように人員が回転する組織は採用対象者に高い経験値を求めないケースが多く、採用対象の年齢層が比較的低い傾向があります。会社に求めるものに対する優先順位は年齢層によって異なるため、保険よりも基本給を重要視する割合が多い比較的年齢層が低い応募者に対しては、保険の充実が必ずしも最善であるとは言えません。
また、アメリカにある中小規模の日系企業の場合、多くが同規模の米系企業よりも基本給が安いと言われている事を踏まえると、保険の充実が競争力に繋がる可能性が高くはないとも考えられます。
つまり、例えば「同業界の米系企業程お金は出せない上、昇格(=昇給)するにもポストがないため、ある程度自社で経験を積んだらステップアップとして他社に移ってくれてやむなし」といったようなジレンマを抱えている組織であれば、保険の充実度よりも基本給に比重を置いた方が競争力は高い場合があるかもしれません。(その場合、経験を積むための研修プログラムや教育制度が用意されているとより効果的です)
では、人の出入りが少ない組織の場合はどうでしょうか。この場合、職務の質や量が変わりにくく、安定して業務を回せるようにする事が重要なポジション、あるいはガツガツ仕事をして中長期的な雇用を視野に入れているポジションなどが想定されます。前者のポジションの場合は、基本給に関しては本来ほとんど変わらないポジションに部類されるため、基本給よりも福利厚生が充実しているバランスが向いており、後者の場合もある程度福利厚生を充実させた上で、昇給および昇格のスキームが重要になって来る事が考えられます。
しかし注意が必要なのが、前回のNews Letterにも書かせていただいた通り、長年勤務している人員の中には給与レンジを無視した昇給を重ねて来てしまっている人もいて、「基本給が市場相場よりも高い上に保険もかなり充実している」といった現象が発生してしまう事もあります。もちろん、それは決して悪いことではありませんが、限られた人件費を効果的に使うのであれば、費やす先のバランスを考える事は重要になります。
保険の充実度に関しては、恐らく日系企業の多くがアメリカに進出した当時(1980年代-1990年代前半)のものに倣い、「充実させるべき」というスタンスが浸透している部分もあるのかと思います。そのため、なかなかそこにメスを入れてまで報酬設計およびそのバランスを見直すという発想に至らない、あるいは時間に余裕が無いなどでアンタッチャブルとなってしまっている部分もあるのかもしれません。(実際、抜本的な変更をした事のある会社は少ないのではないでしょうか)
報酬バランスを考える上で最も重要なのは、組織の生産性や従業員のモチベーションを高めるために、必要な所に必要なお金を費やすという事になります。保険が充実している事が必ずしも競争力が高い訳ではなく、場合によっては過剰な厚遇になってしまっている事なども踏まえ、基本給と保険が現状の自社組織にとって本当に必要なバランスになっているのかどうかを検証し、経営を考える要素の一つとして捉えてみてはいかがでしょうか。
本内容は人事的側面から実用的な情報を提供するものであり、法的なアドバイスではありません。また、コンテンツ(文章・動画・内容・テキスト・画像など)の無断転載・無断使用を固く禁じます。