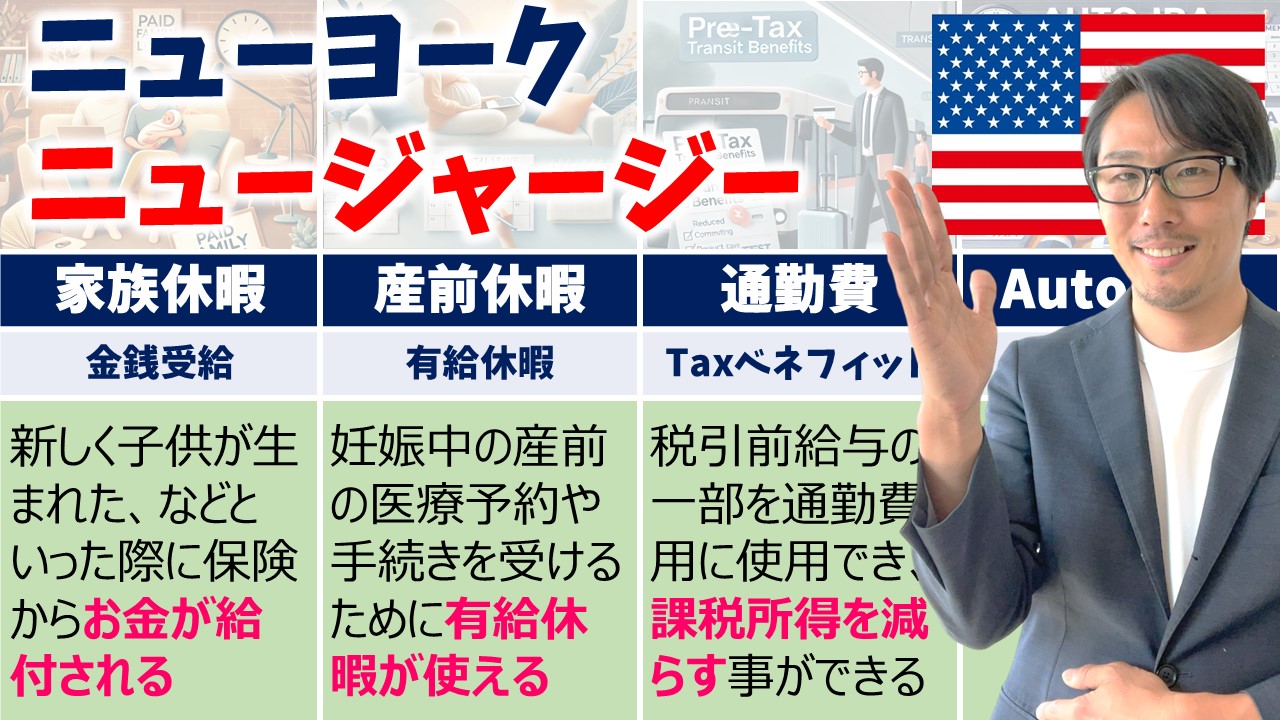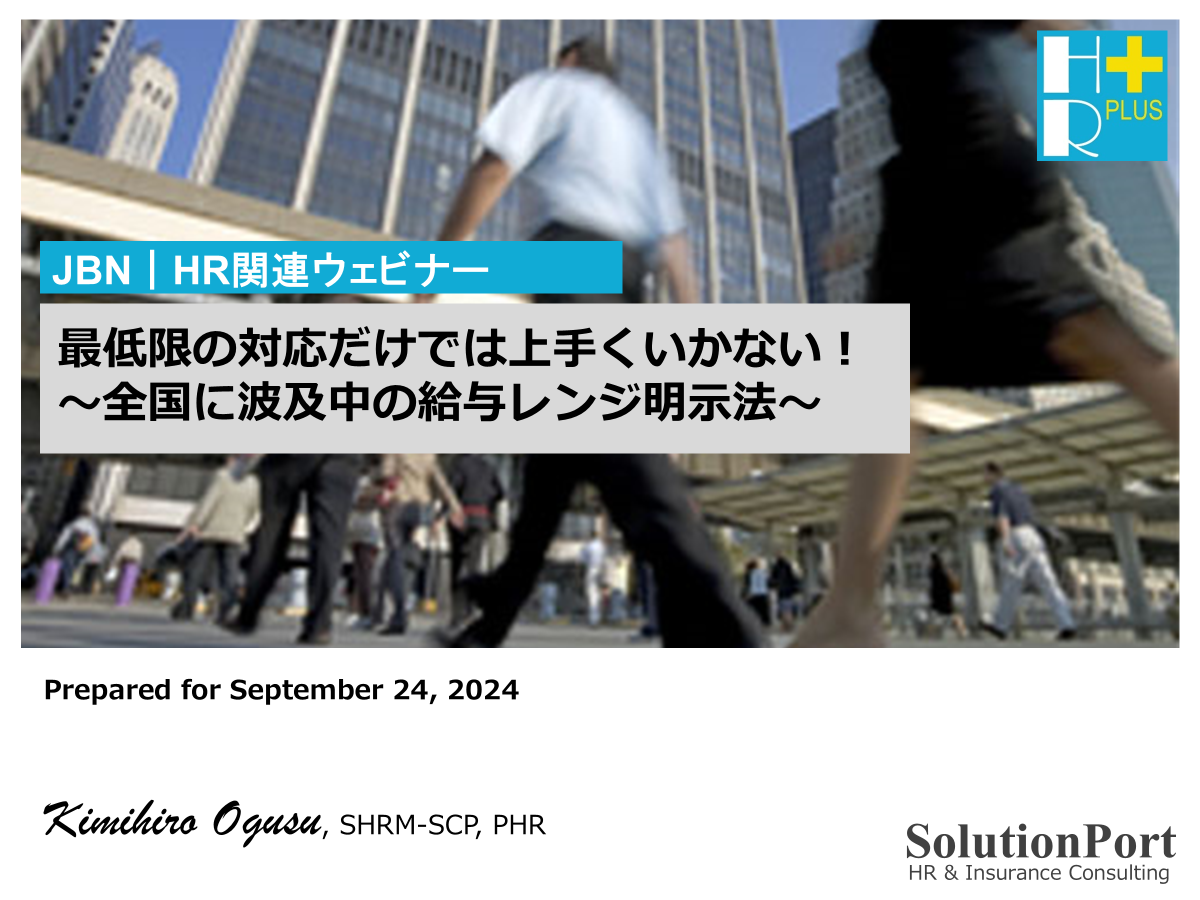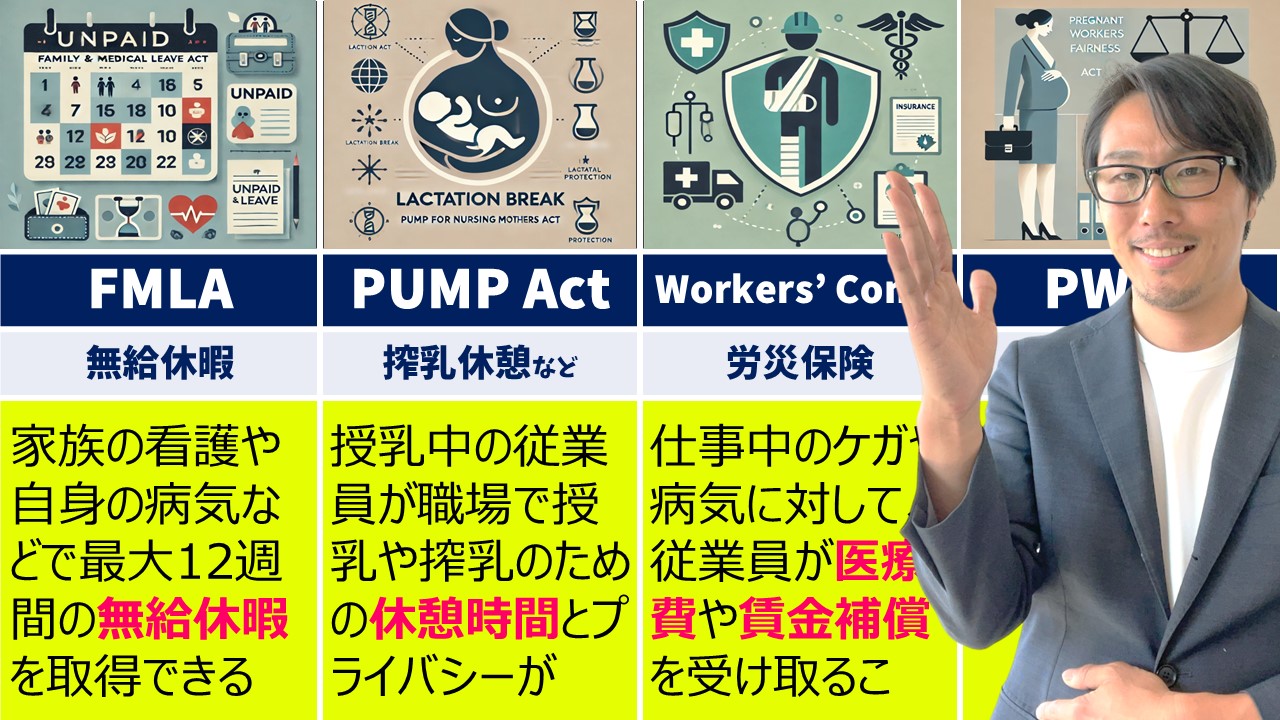Kimihiro Ogusu|2016年
前回に引き続き、人事制度に内在するオペレーションとコンプライアンスの両側面から、一般的な制度や施策を見て行き、何故それらが重要であるのかを考察していきます。
よく耳にするものとして3つ目に挙げさせていただきたいのが報酬設計です。前回のNewsLetterに記載した通り、アメリカでは、会社は「お金を得るための場所」「生活のための手段」という意味合いが強く、仕事の職務内容や責任範囲と「貰えるお金」が強く結びついています。
そのため、給与は従業員ごとに適正な額が与えられている事がまずは重要となり、昇給やボーナスがモチベーションを保つあるいは向上させる事ができる様な形になっていると更に良い状態と言えます。つまり、現在の給与やボーナスなどに関して、その額面に妥当性や正当性が備わっているのかがポイントとなります。
コンプライアンス面としては、最低賃金や残業代などが法律に沿っているかどうかに加え、昇給やボーナスの際に用いられる一定の基準の様なものがあると、差別と捉えられる要素を少なくする事ができます。例えば給与交渉で揉めた際、人種・性別・宗教あるいは好みで決めているのではなく、市場水準との比較や事前に定めている社内のきまりにしっかりと沿っているものであると示す事が可能となります。
ちなみに、日系企業の基本給(entry/intermediate)は全米の給与相場よりも低い事が多いとされる点*1や、最近の最低賃金の引き上げ傾向*2、また12月1日から適用されるFLSAのExemption定義*3を考慮すると、現在の自社組織にあるポジション(肩書ではなく職務内容/責任範囲)に対する適正な給与水準を知る事は非常に重要で、その水準と現在の給与額に乖離があれば、再考すべき部分がある状態とも考えられます。
*1 エンジニアなど一部の業種や勤続年数が長い従業員は除く
*2 2018年を目途に全国の最低時給を$10.10にする(現在$7.25)、NYのファーストフード大手チェーンの最低時給が$15.00になる事など
*3 Exemptと定義するには職務内容と最低年収(=$23,660、12月からは$47,476)の合致が必要
最後に評価に関して挙げさせていただくと、こちらはパフォーマンスを測るものというイメージが先行しがちかと思いますが、人事記録などコンプライアンス面としても必要不可欠なものです。皆さまのイメージの通り、従業員の行動や成果に関して意見交換をするツール、昇給やボーナスを決める際の物差しとして社内の業務やモチベーションなどをコントロールしうるものである一方、解雇や昇給/昇格などの決定事項の裏付けとして公正な仕組みと記録がある事が、コンプライアンス面として非常に重要になります。
例えば、解雇に関して考えてみると、アメリカはAt-Will (任意雇用)で成り立っているため、雇用側や従業員側がいつ何時でも雇用関係を解消できる事になっていますが、場合によってはこの人事記録が無いと解雇が難しくなる、あるいは揉めてしまった時に正当性を証明できなくなってしまいます。
これは特に、ポジションによって人種や年齢の偏りが出てしまいかねない中小規模の組織や、マネジメントなど一定レベル以上の役職者が日本からの出向者で固められている日系企業に起こりやすい問題なので、注意が必要です。(解雇の対象者がたまたまマイノリティとされるカテゴリーの人であった場合に問題が大きくなる事も考えられます)
また問題点としては、どの組織も評価フォームやそれに準ずるものを持っている事がほとんどですが、「実用性があまり無い」と耳にする事が多い部分にあります。そういった場合は、例えば日本から持ってきた制度や以前作成したフォームに内容を当てはめる形で記載しているケースなど、必ずしも現状に沿った形で運用できていない事が考えられます。
本来は、組織がやりたい事や各従業員に行って欲しい事があり、それが実行されやすくなるためにフォームがあるので、フォームの形や項目はその内容をまとめていく過程で形成されるものなのかもしれません。つまり、場合によっては点数を着ける様な従来の評価制度ではなく、チェックリストの様な簡易的な形の方が適している事もあるのかと思います。
いずれにしろ、今回のポイントは「人事制度はオペレーション面 (社内最適)とコンプライアンス面の両方がある」という事と、各制度の「いる/いらない」を片一方の要素にばかり着目して判断していないかという点になります。
これを機に、皆さまが現在運用されている制度の両側面を再度見ていただき、しっかりとした人事制度を整備するための確認ポイントとされてみるのはいかがでしょうか。
本内容は人事的側面から実用的な情報を提供するものであり、法的なアドバイスではありません。また、コンテンツ(文章・動画・内容・テキスト・画像など)の無断転載・無断使用を固く禁じます。