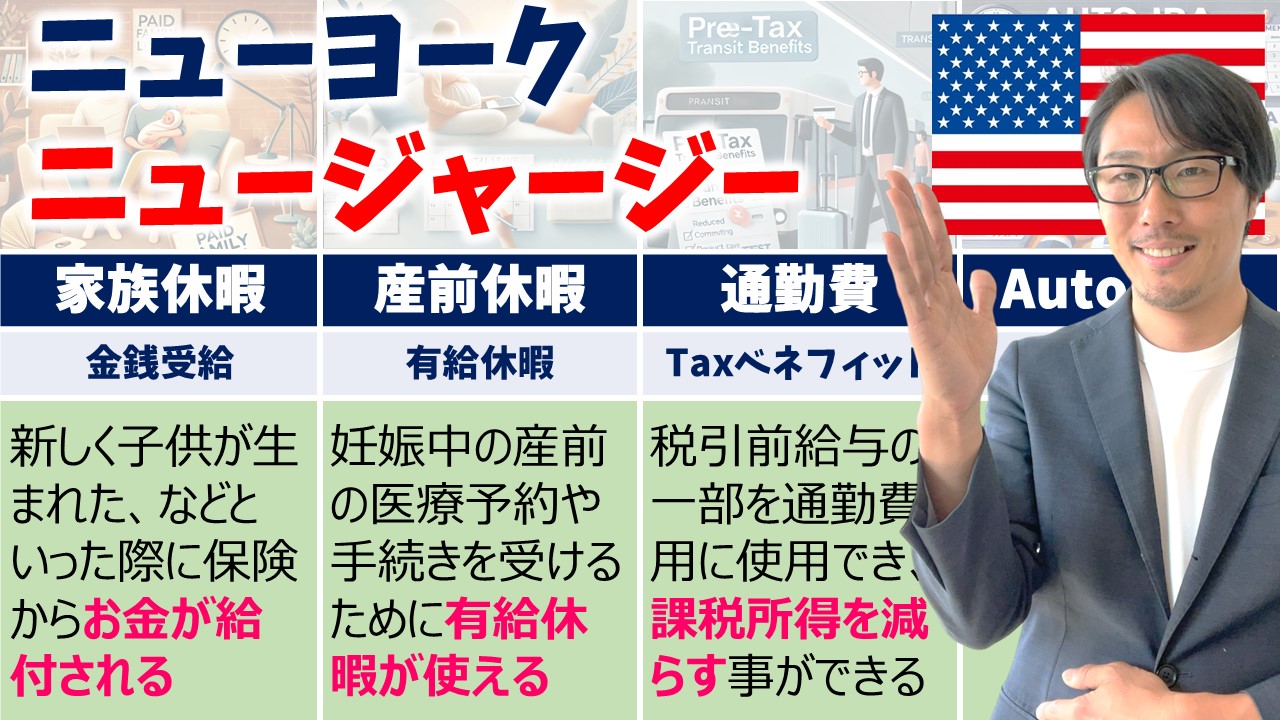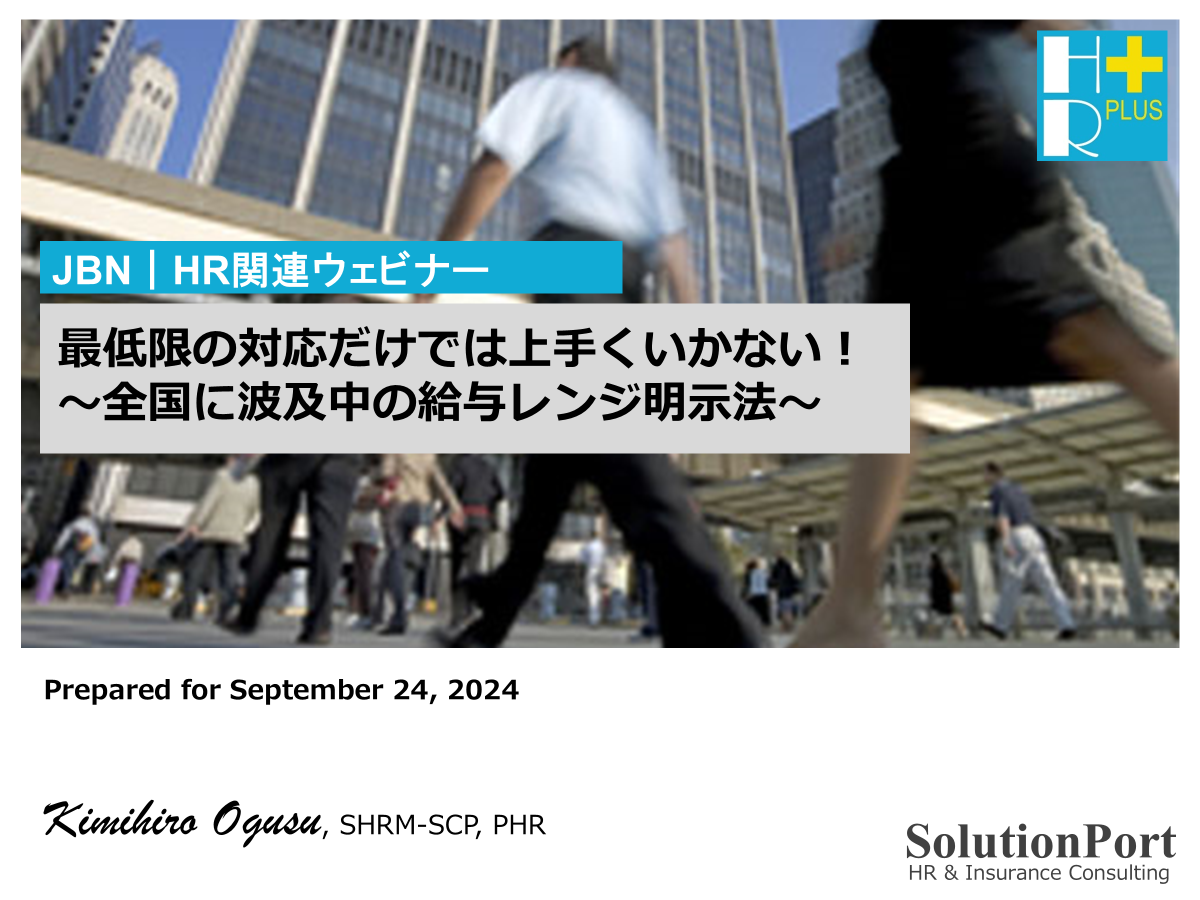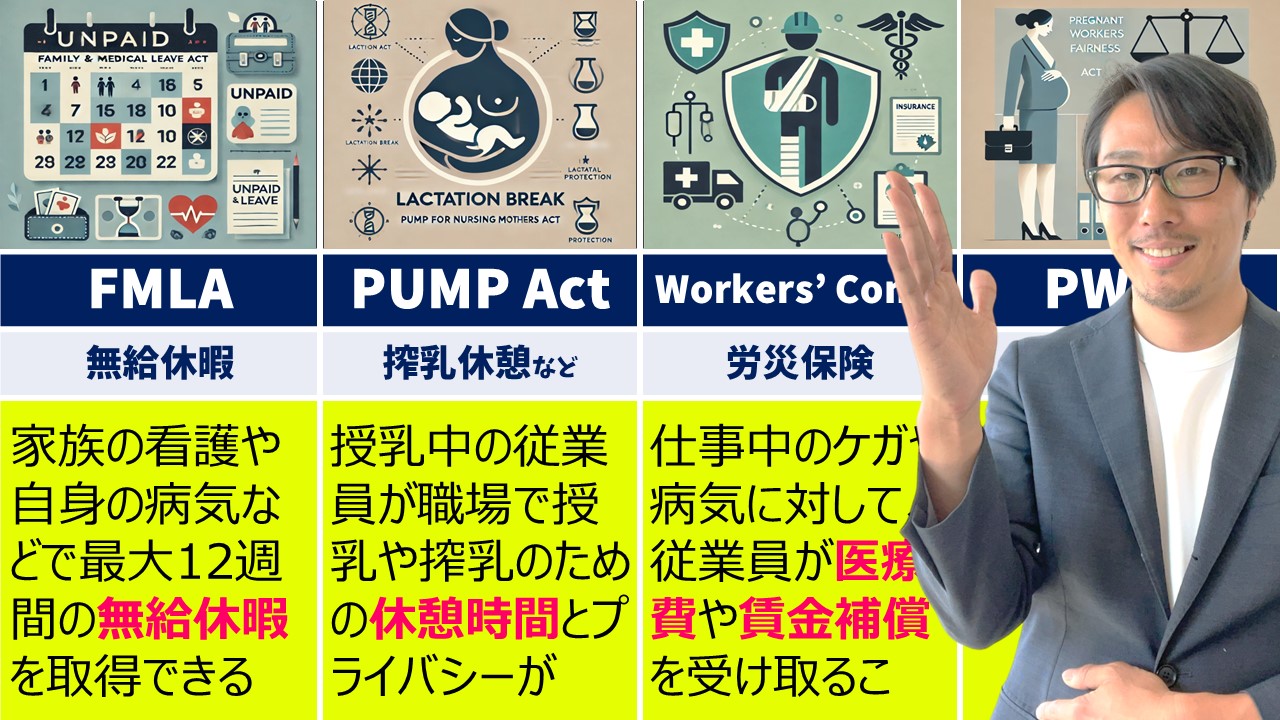Kimihiro Ogusu|2016年
身近で入手できる数字の危険性
2016年もいよいよ残す所あと2ヶ月となりましたが、この時期になると次年度の昇給の話をよく耳にする様になります。そのため、昇給の参考になりそうな情報を探される方も多いかと思いますが、データの集め方には少し注意が必要になります。
最近は情報源も多様で、インターネットや書面にある数字やセミナーで聞くデータ、人材エージェントが口にする話など、身近な所で入手できる事もあります。数字というのは一見納得性が高いため、妄信的にそれに従いたくなってしまいがちですが、扱い方を間違えてしまうと思わぬ落とし穴に陥ってしまうケースも考えられます。
入手した数字がどういったもので、自社の状況を踏まえた上で参考にする部分はどこにあるのかという事が重要であり、状況によってはその数字は参考にならない、あるいは参考にしてはいけないケースも在り得ます。
例えば、仮に日系企業の給与をまとめているデータがあった場合、それはどの様に参考にすれば良いのでしょうか。基本給を考える上では、会社の業界/業種、拠点が置かれている地域、対象者の職務内容が重要になりますが、そういった情報が細かく載っていないのであればその数字に使い道はあまり無く、あるとするならば、対象ポジションの職務内容が明確で、かつ日系企業同士で優秀な人の引き抜き合いをしているポジションのみになります。
また、コミッションベースで働いている米系の人材エージェントなどは、実際の相場よりも高い給与を提示する事もあれば、転職サイトで見れる給与データも少し高めに出て来る事が多いそうなので、気を付けなくてはなりません。
データの扱いミスによる典型的な事例
以前のニュースレターで挙げさせていただいた事がありますが、次年度の昇給を考えるにあたってCPI (Consumer Price Index = 消費者物価指数)の数字を反映させる事が正しいと思われがちなものの、実際は直接的な影響はなく、どちらかというと昇給率のトレンドを参考にする事の方が一般的です。
「毎年3%ずつ昇給している」あるいは「最低限CPIの率は毎年昇給させて来た」という日系企業は多く、これも情報の参考の仕方を間違えてしまっている例であり、その結果として会社に長年勤めている従業員の給与が市場相場を大幅に超えているケースというのをよく耳にします。
本来であれば、市場相場から導き出された給与レンジがあって、評価に応じた昇給率の違いがあるという上で初めて昇給トレンドを反映させるべき所を、その前提が抜けてしまっているために目の前の数字ばかりに捉われてしまった結果なのかもしれません。
セミナーなどで話を聞く際の注意点
この時期はCPIや失業率、昇給率などをトピックにしたセミナーも多いかと存じますが、参加する場合はその話にどの様なメッセージがあるのか、つまりそれらの数字をどの様に解釈すれば良いのかを説明してくれているかどうかが重要なポイントになります。
もしもその話にメッセージ性が欠けているのであれば、聞き手側が内容を上手に受け止める事が重要で、その数字が自社にどう関係して来るのかをイメージする必要があります。
また、昇給に関してはここ何年も同じ傾向が続いているため、トレンドを聞く事よりも自社の現在の状況を把握する事の方が大事になって来ます。次年度の昇給予算はCPIに関係なく3%前後の上昇があると予想されており、評価に応じて昇給が1%未満の人がいれば3%以上の人もいるという事を踏まえた上で、自社の対象者の現在の給与が市場水準と比較してどうなのか、また給与レンジの上限に近づいているのであれば昇給率は低くなるという考えが一般的です。いずれにせよ、キーとなるのは現状把握になるため、基本給の市場ベンチマーキングは有効な手段となります
少し話は逸れますが、大航海時代にヨーロッパの人々がアメリカ大陸を”発見”した際、それまでヨーロッパ社会には無かったものが多く持ち帰られ、その中にジャガイモがあったと言われています。王室に、”実を食べるもの”と紹介された結果、”毒素のある植物”と誤認されしばらく見向きもされないものだったそうです。今では外食では見かけない事がない程一般的な食べ物ですが、現地でジャガイモを見て持ち帰った人が使い方を間違ってしまったために、普及が遅れてしまったという事です。
情報を入手した際は正しく理解する事が重要で、特に数字に関してはそれが何を意味していて、どの様に参考にするべきなのかをよく吟味する事が失敗しないための秘訣なのかと思います。
本内容は人事的側面から実用的な情報を提供するものであり、法的なアドバイスではありません。また、コンテンツ(文章・動画・内容・テキスト・画像など)の無断転載・無断使用を固く禁じます。